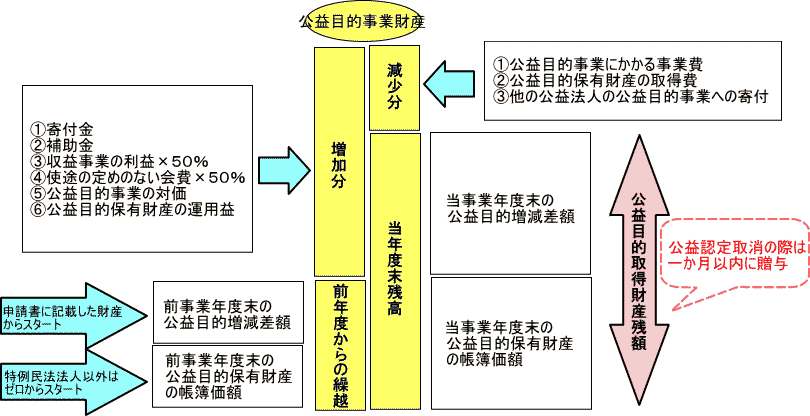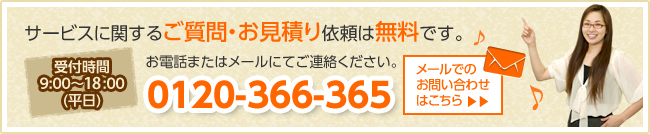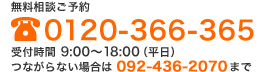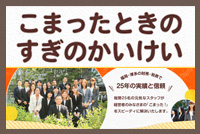TOP > 公益認定基準
新公益法人の公益認定基準のまとめ
公益法人制度改革の概要
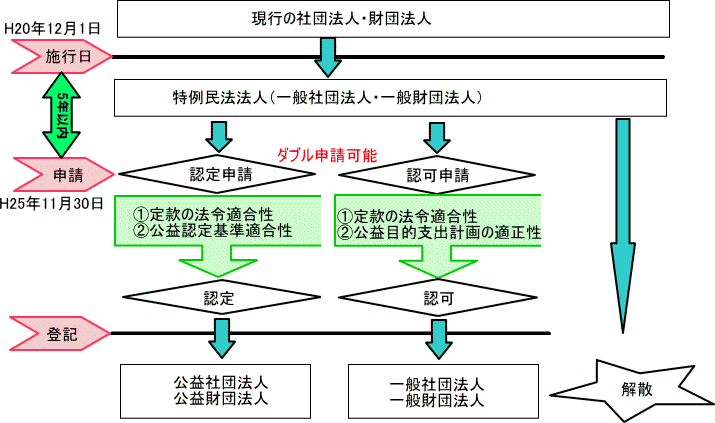
公益認定の基準
- 1.公益目的事業を行うことが主たる目的であること
- 公益目的事業の要件(23業種+公益目的事業チェックポイント)
- 2.公益目的事業に必要な経理的基礎と技術的能力があること
- 財務基盤の明確化、経理処理・財産管理の適正性、情報開示の適正性および事業実施のための技術・専門的人材・設備
- 3.理事、社員などの法人関係者に特別の利益を与えないこと
- 「特別の利益」とは利益を与える対象の選定や利益の規模が、事業内容や実施方法等具体的な事情に即し、社会通念に照らして合理性を欠く不相当な利益の供与その他の優遇をさす。
- 4.営利事業者、特定の者の利益を図る活動を行う者に特別の利益を与えないこと
- 「特別の利益」は同上
- 5.社会的信用を維持する上でふさわしくない事業および公序良俗に反する事業でないこと
- 投機的的取引、利息制限法上の無効となる金利による融資事業、性風俗関連特殊営業
- 6.公益目的事業の収支相償
- 公益目的事業の経常増減額がマイナスであること
- 7.公益目的事業以外の事業が公益目的事業の実施に支障のないこと
- 収益事業への資源配分や事業内容如何により公益目的事業の円滑な実施に支障がないこと
- 8.公益目的事業比率が50%以上見込まれること
- 公益目的事業経費/(公益目的事業経費+収益事業経費+法人運営経常経費)≧50%
- 9.遊休財産額が年間の公益目的事業費相当額を超えないと見込まれること
- 遊休財産の定義、公益目的保有財産の定義
- 10.理事、監事は同一親族関係者が総数の3分の1以下でなければならない。
- 本人、配偶者、三親等内親族、内縁関係者、使用人、理事から受ける金銭で生計を維持する者、その配偶者、その三親等内の親族
- 11.理事、監事は同一企業等の関係者が総数の3分の1以下でなければならない
- 他の団体の役員および使用人・職員
- 12.会計監査人を設置していること
- 最終事業年度の収益、費用および損失の額が1000億円、負債の額が50億円にいずれも達していない法人をのぞく
- 13.理事、監事、評議員の報酬等を不当に高額とならないよう支給基準を設定すること
- 勤務形態に応じた報酬等の区分、額の算定方法、支給の方法・・・
- 14.社員の資格の得喪や議決権に関し不当な差別的な取扱いをせずに、理事会を設置していること
- 法人の目的、事業内容に照らして判断
- 15.他の団体の意思決定に関与することができる株式その他内閣府令で定める財産を保有していないこと
- 他の団体の意思決定機関の議決権の50%以下であれば保有してもよい
- 16.公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、一定の事項を定款で定めていること
- 公益目的事業不可欠特定財産の存在の旨、維持、処分の制限等→計算書類上「基本財産」として表示
- 17.公益認定取り消しの場合に「公益目的所得財産残額」を一か月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与する旨の定款の定め
- 国・地方公共団体、学校法人、社会福祉法人、独立行政法人、その他公益法人
- 18.清算の場合の残余財産を類似の事業を目的とする公益法人等に帰属させる旨の定款の定め
- 同上
公益目的事業の要件
| 23業種のどれかに該当すること | 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与 | |
|---|---|---|
|
☆事業区分ごとの公益目的事業のチェックポイント
|
★17の事業区分に該当しない場合 (1)事業目的の公益性 (2)事業の合目的性
|
| ※その法人の全ての事業が公益目的である必要はない。 | ||
経済的基礎と技術的能力
| 経理的基礎 | 財政基盤の明確化 | 貸借対照表、収支予算書は、財務状態を確認し、法人の事業規模をふまえ、必要に応じて今後の財務の見通しについての説明ができること |
法人の規模に見合った事業実施のための収入が適切に見積もることができること
|
||
| 経理処理・財産管理の適正性 |
|
|
| 情報開示の適正性 |
|
|
| 技術的の能力 | 専門的な人材や設備などの確保 | |
理事、社員などの法人関係者
- 理事、監事、使用人
- 社員・基金拠出者または設立者・評議員
- 上記の配偶者または三親等内の親族
- 上記の内縁関係者
- 1〜2の者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者
- 法人の社員、基金の拠出者または財団の設立者が法人である場合には、その法人が事業活動を支配する法人として内閣府令で定めるもの、またはその法人の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるもの
営利事業者、特定の者の利益を図る活動を行う者
- 株式会社その他の営利活動をおこなう者(収益事業を行う非営利法人を含む)に対して寄付その他特別の利益を与える活動を行う個人または団体
- 社員その他の構成員または会員もしくはこれに類するものの相互の支援、交流、連絡その他の社員等に共通する利益を図る活動を主たる目的とする団体
公益目的事業については収支相償
第1段階
事業の目的や実施の態様等でグルーピングした事業ごとに収支相償であるか(経常収益<経常費用)
| 公益目的事業A | 公益目的事業B |
| クリア | 不合格 |
第2段階
公益目的事業にかかる会計全体での収支相償
収益事業利益の50%ちょうどを繰り入れる場合
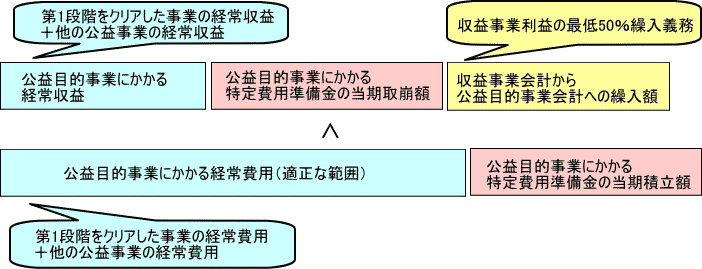
収益事業利益の50%を超えて繰り入れる場合
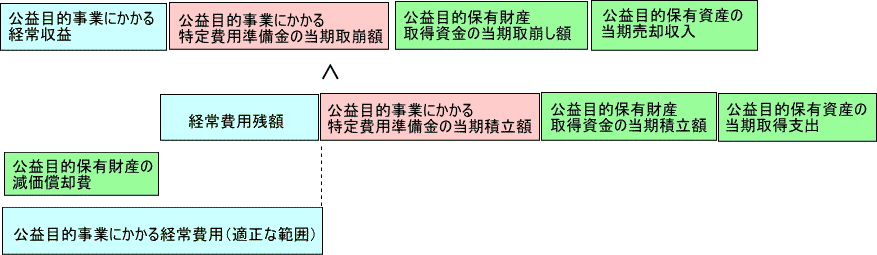
※ある事業年度において剰余が生じる場合において、公益資産取得資金への繰入(積立)や当期の公益目的保有財産の取得等に充てたりする場合には、本基準は満たされているものとして扱う。
このような状況にない場合は、翌年度に事業の拡大等により同額程度の損失となるようにする。
公益目的事業比率が50%以上
| 基本的には、正味財産増減計算書の経常費用の部の数値を用いるが、下記3点について計算書類から離れて調整計算し、事業費率に算入可能 | |
|
| 正味財産増減計算書 | |||
| 公益目的事業会計 | 収益事業会計 | 法人会計 | |
| 経常費用 | |||
| 事業費 |
|
|
総務、会計、人事、厚生等を行う管理部門の経費(人件費、事務所賃料、水道光熱費等)→「管理部門費用」 |
| 管理費 | 該当なし | 該当なし | 総会・評議員会・理事会の開催運営費、理事・評議員・監事報酬、会計監査人監査報酬 |
| ※事業費と管理費に共通する費用は合理的な基準により配賦する。 | |||
遊休財産額が年間の公益目的事業費相当額を超えない
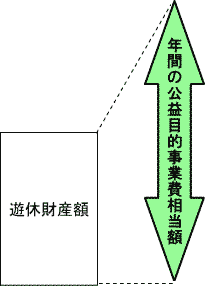 |
●「年間の公益目的事業費相当額」 | =正味財産増減計算書上の公益目的事業費+特定費用準備資金への積立額 |
| ■「遊休財産額」 | =総資産−負債−(控除対象資産※−対応する負債) =一般正味財産−(使途の定まった財産−これに対応する負債) |
|
| ◆「控除対象資産」 |
|
| 貸借対照表 | 財産の使途・保有目的 | 認定去の財産区分 |
|
| (流動資産) | 現金預金 | 具体的な使途の定めがないもの | 遊休財産 |
| 特定事業積立資産 (短期特定費用準備金) |
公益目的事業で生じた剰余金で翌年度に費消することが約されているもの | 特定費用準備資金 | |
| (固定資産) 基本財産 |
土地・建物等 | 公益目的事業実施のために保有 | 公益目的保有財産 |
| 公益目的事業を支える収益事業財産 | 収益事業・管理活動財産 | ||
| ○○基金(預金・有価証券等) | 公益目的事業に果実を充当 | 公益目的保有財産 | |
| 単に公益目的とのみ定款で定め、積み立てているもの | 遊休財産 | ||
| 展示資料 | 博物館展示に不可欠な特定の財産 | 公益目的保有財産 (不可欠特定財産) |
|
| 特定資産 | 土地・建物等 | 公益目的事業実施のために保有 | 公益目的保有財産 |
| 管理費に収益を充当(適正な範囲に限る) | 収益事業・管理活動財産 | ||
| 寄附を受けた財産で寄附者の定めた使途に従っていないもの | 遊休財産 | ||
| 預金・有価証券等 | 公益目的事業に果実を充当 | 公益目的保有財産 | |
| 管理費に果実を充当(適正な範囲に限る) | 収益事業・管理活動財産 | ||
| 修繕積立資産 (資産取得資金) |
公益に使う建物の大規模修繕のために積み立てているもの | 資産取得資金 | |
| B事業実施積立資産 (特定費用準備資金) |
公益目的事業拡充に備え積み立てているもの | 特定費用準備資金 | |
| その他固定 資産 |
土地 建物 構築物 |
公益目的事業を支える収益事業財産 | 収益事業・管理活動財産 |
| その他 | 遊休財産 | ||
公益目的事業財産