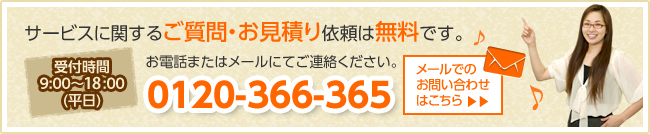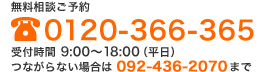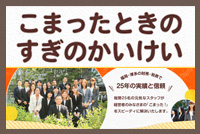TOP > 一般財団法人の設立
いままではNPO法人を立ち上げることが一般的でしたが、平成20年12月から新しく「一般財団法人」の制度ができました!
NPO法人はその活動内容が17種類の特定非営利活動に限定され、半年くらいかけて主務官庁の認証をうけなければなりませんが、一般社団法人は、収益事業をはじめとしてどんな仕事をしてもかまいませんし、主務官庁の認可等も一切不要であり、登記をするだけで法人を設立させることができます。ただし、社会的な信用はまだまだNPO法人の方が高いかもしれませんが、いまからどんどん増えていきますよ。
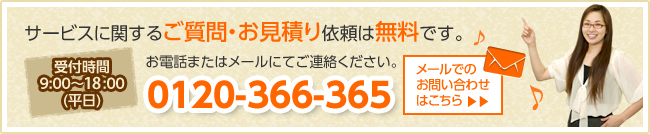
一般財団法人の設立
一般財団法人って?
「地域の社会貢献がしたい!」「町のおじいちゃん、おばあちゃんに喜んでもらえる仕事がしたい!」とお考えのみなさん。いままではNPO法人を立ち上げることが一般的でしたが、平成20年12月から新しく「一般財団法人」の制度ができました!
NPO法人はその活動内容が17種類の特定非営利活動に限定され、半年くらいかけて主務官庁の認証をうけなければなりませんが、一般社団法人は、収益事業をはじめとしてどんな仕事をしてもかまいませんし、主務官庁の認可等も一切不要であり、登記をするだけで法人を設立させることができます。ただし、社会的な信用はまだまだNPO法人の方が高いかもしれませんが、いまからどんどん増えていきますよ。
一般財団法人とNPO法人の違い
| 一般財団法人 | NPO法人 | すぎのコメント | |
| 認可 | 認証不要 | 事務所が単一都道府県→都道府県知事の認証 事務所が複数都道府県→内閣総理大臣の認証 |
時間と手間をかけて社会的信用をとるか すぐにでも活動をはじめたいか |
| 設立期間 | 2週間 | 半年くらい | |
| 発起人数(社員数) | 1人以上 | 10人以上 | |
| 事業活動 | 自由 | 特定非営利活動(17種類)に限定 | |
| 登記費用 | 公証人手数料 約50,000円 登録免許税 約60,000円 |
公証人手数料 なし 登録免許税 なし |
|
| 資本金 | 300万円以上の拠出金 | 不要 | 基本財産となります 現金でも現物でも可 |
| 役員数 | 理事3人以上 監事1人以上 評議員3人以上 |
理事3人以上、監事1人以上 (報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること) |
一般社団法人よりもガバナンスが求められる。 |
| 法人税 | 「非営利型法人」→収益事業課税 OR 「普通法人型」→全所得課税 |
収益事業課税 | 収益事業課税は、 税理士の中でも得意・不得意が分かれる 特殊な分野です。 |
| 税率 | 株式会社と同じ | 株式会社と同じ | |
| 寄附金税制 | 「非営利法人型」→優遇措置あり | なし | 法人に寄付をした人または会社が その寄付を損金にできるかどうかの問題 |
| 主務官庁への報告 | なし | 事務所が単一都道府県→都道府県知事に報告書提出 事務所が複数都道府県→内閣総理大臣に報告書提出 |
|
| 法人格の取り消し | 2年連続で純資産額が300万円をきったら解散 | 認証の取り消し | |
| 行政からの認知度 | まだ低い | 高い |
一般財団法人の設立手順
| 要件 | すぎのコメント | |
| 法人名を決める | 「一般財団法人○○○」 「●●●一般財団法人」 |
法人名はカタカナでもローマ字でもOK。 |
| 拠出金の準備 | 300万円 | 一般社団法人の「基金」は返還できますが、一般財団法人の拠出金は返還不可です。 |
| 役員を決める | 理事3人以上 監事1人以上 評議員3人以上 |
|
| 定款をつくる |
|
この定款の作り方ひとつで、 法人税法上の「普通法人型」か「非営利法人型」が決まってしまうので、かならず専門家の意見を聞くこと。 ※定款には設立者全員の署名または記名押印が必要 |
| 印鑑証明を取り寄せる | 設立者全員の印鑑証明 代表理事の印鑑証明 |
各自2部づつが無難 登記申請予定日から3ヶ月以内に取得したもの |
| 定款の認証 | 定款3部と印鑑証明をもって公証人役場で認証をうける。 | 設立時社員全員の署名または記名押印が必要 |
| 財産の拠出 | 指定口座に金銭の振込 | |
| 印鑑の作成 | 法人の代表印 (銀行印、角印) |
設立登記の前に準備すること |
| 登記申請 |
|
提携の専門家の先生が迅速にそろえます。 |
| 登記簿等の取得 | 法務局にいき、「登記簿謄本」「印鑑カード」「印鑑証明書」を取得 | これを持って、各役所の法定届け出をする。 |
一般財団法人の社員・機関
一般財団法人の評議員
| 定義 | 理事のお目付け役 |
| 人数 | 設立時3人以上 |
| 欠格事由 |
|
| 任期 | 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで |
| 選任・解任 | 定款に記載 但し、理事または理事会が評議員を選任、解任する旨の定めは無効 |
評議員会
| 回答 | すぎのコメント | |
| 定義 | 一般財団法人の評議員で構成される最高意思決定機関 | |
| 制限 | 法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。 | 法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その 他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。 |
| 種類 |
|
通常は理事会の決議により評議員会を招集するが、評議員が裁判所の許可を得れば勝手に評議員会を招集することができる。 |
| 普通決議 | (1) 理事の選任及び解任 (2) 役員等の報酬並びに費用の額の決定 (3) 各事業年度の事業報告及び決算の承認 (4) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け (5) 前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及びこの定款に定める事項 |
議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数 ※特別利害関係のある社員は決議に参加できない。 |
| 特別決議 | (1) 監事の解任 (2) 定款の変更 (3)役員等の責任の一部免除 (4) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡 |
議決に加わることができる評議員の3分の2以上 |
| 議決権 | 評議員ひとりに1個の議決権 | |
| 議決権行使方法 |
|
評議員の全員が、決議の目的事項の提案に同意の意思表示をしたときは、評議員総会の開催を省略することができる。 |
理事
| 定義 | 会社でいうところの取締役 |
| 欠格事由 |
|
| 理事の数と代表権 |
理事3人以上が必要で、理事により理事会を設置し 、理事会で代表理事を選任する。
|
| 理事の選任方法 | 評議員会の普通決議 |
| 解任 | 評議員会の普通決議 |
| 任期 | 選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会終結の時まで |
理事会
| 回答 | すぎのコメント | ||
| 定義 | 全理事で構成される業務執行決議機関 | ||
| 職務 |
|
||
| 専決事項 |
|
理事会が理事に委任することができないという意味 | |
| 種類 |
|
定款で毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上その報告をしなければならない旨を定めることも可能 | |
| 決議 | 理事の過半数が出席し、その過半数 |
特別利害関係のある理事は議決に参加できない | |
| 議決権行使方法 |
|
理事の全員が、決議の目的事項の提案に同意の意思表示をしたときは、理事会の開催を省略することができる。(定款の記載必要) | |
| 議事録 | 出席した理事(定款で議事録に署名し、または記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事をする旨を定めている場合にあっては、当該代表理事)及び監事は、これに署名するか、または、記名押印しなければならない。 |